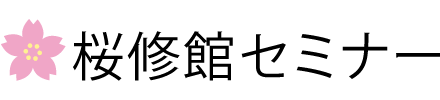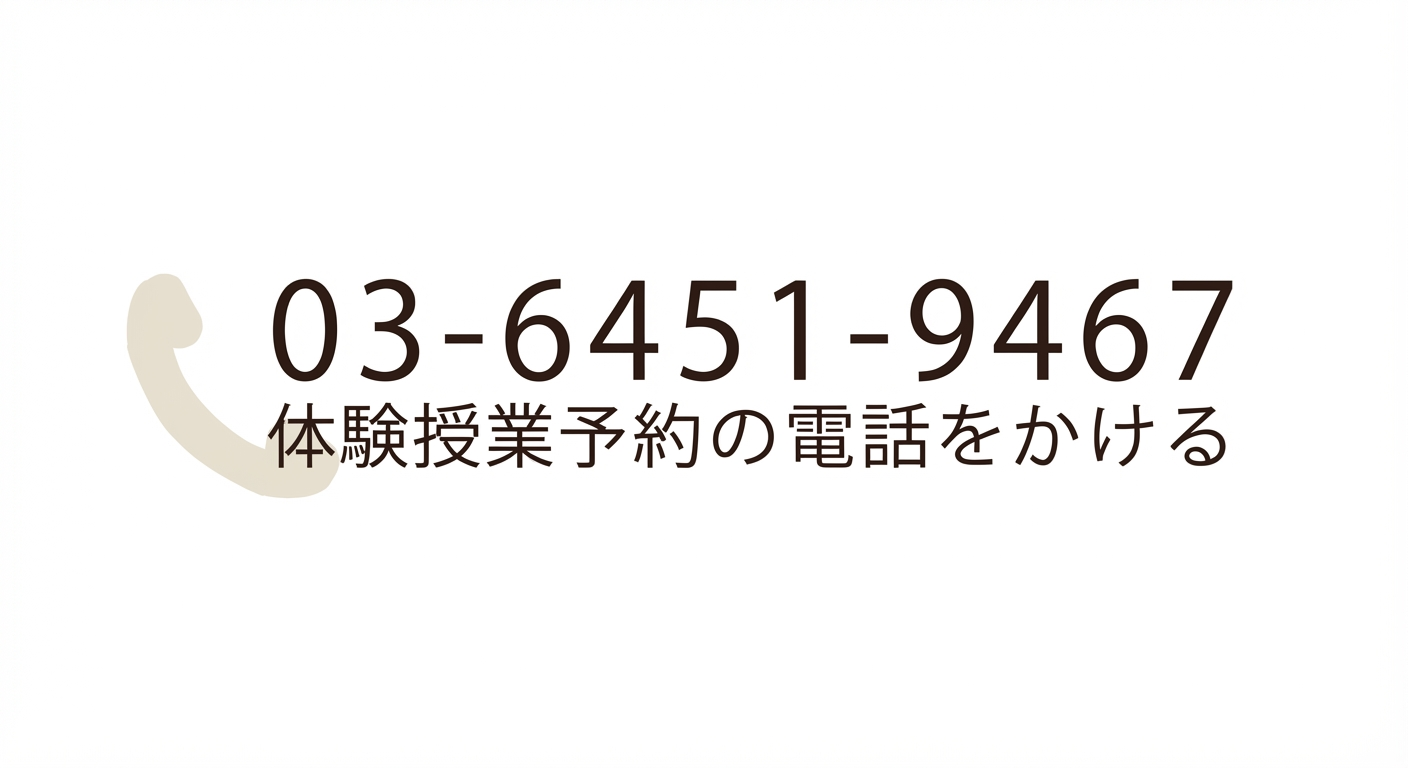第13回 子どもの学力は低下し続けているのか? 〜
ここ数年、塾・学校関係者から、「子どもの学力が年々低下している」という声をよく耳にします。
「子どもが一生懸命伝えようとしてくれているが、なんの説明をしているのかわからない。」
「文章が読めない。そもそも漢字が読めない。」
「文字や式が書けない。」
具体的には、こうした悩みを聞くことが多いです。
考える力を重視する桜修館受検生の保護者としては、看過できない問題でしょう。
子どもの学力が低下したと言われる理由は?
果たして、子どもの学力は本当に低下しているのでしょうか。
桜修館セミナーでは、子どもの学力が真に低下したとは考えていません。
では、なぜ教育関係者は同じ危機感を持っているのか。
実は、子どもが実際に失っているのは学力や思考力ではなく、「考える機会」ではないでしょうか。
コロナ禍、GIGAスクール構想のもと、公立の小学生には1人1台タブレットが配布されました。
課題提出は家からClassroomが当たり前になり、教育AI Qubena(キュビナ)が問題を生成してくれるようになりました。
いままで、三田国際や青稜など一部私立で先進的に行われてきたことが、全国レベルで広がったのです。
すると、今まで対面授業で当たり前に行われていた、みんなの前で自分の意見を発表する機会の一部が、タブレット提出に代わってしまいました。リアルタイムで同期していた意見はタブレット上で非同期になり、実際に口に出す代わりにチャットで担任の先生と話す機会もコロナ前より格段に増えました。
今まで、LINEやYoutubeの使い方を間違えて児童間トラブルになっており、一部で禁止の方向に傾きつつあったネットリテラシーは、もはや必須のものとなりました。
このような変化は、大人であれば、リモートワークやライフワークバランスなど、メリットを受けられる方が多いです。
しかし、仮に大人であっても、新入社員や転職直後で周りから技術を教わりたいとき、リモートワークはコミュニケーション上の弊害になることがわかってきています。
まして、小学生がこの変化から受けるダメージは計り知れません。
ネットの書き言葉とリアルの話し言葉のわからない子が増えています。
SNSでは文字や画像・動画を使って本音が言えても、面と向かって他の子に本音の言えない児童が増えました。
そのような中で、それこそ桜修館が求めるような論理的思考力・表現力だけが残っていると考えるほうが不自然です。
かくして、アフターコロナにおいて教育のあり方が変わってしまったことが、子どもの学力が低下したと言われる原因ではないでしょうか。
桜修館受検の良いと感じる点
桜修館受検では「考える力」が求められます。
他の私立中学では、現時点では、暗記したことをアウトプットする、暗記寄りの部分がまだ強いです。そのため、「考える力」を養成する事ができる桜修館受検は子どもに良い影響を与える事ができると感じています。
桜修館受検において、「考える」点で必要な力は次の3つです。
①読み取る力
②考える力
③書く力
①読み取る力
班活動や口頭発表の機会が減り、話す・書く練習が足りなくなりました。検索や動画で即答に触れやすくなり、理由を作る時間を確保しづらくなりました。
そのため、読んでも”理解できない”ことが多くなってしまいました。対策としては、日常生活において、「なぜそう言えるのか」の理由を受検生自身に言わせること、ものごとから情報を読み取る手順を考えること、すなわち、「読みとる力」をトレーニングすることです。
②考える力
ただ考えれば良いという訳ではありません。①を、読んだ内容をふまえて「考える」ことです。また、どうしてこの問題が出てくるのか、相手がどのような答えを出して欲しいのかを”考える”ことです。
③書く力
近年、「解答を答えられない」という事を感じる事が増えてきました。具体的には、問題用紙では正しい答えを導き出せているのに、解答用紙に誤った答えを記入してしまっている事などです。「ケアレスミスだから!」や「次は大丈夫!」などという子は、合ってるのにまた、違う答えを解答用紙に書いてしまいます。特にこれは年々、増えていると感じます。
まとめ「考える力」をつけるための2つの方法
以下2点に心掛けてください。
①「なぜ?」「どうして?」の視点から考えること
②桜修館セミナー、「考える力」を養う塾で学ぶこと
さぁ、しっかり対策を行い、
桜修館中等受験合格を勝ち取ろう!
受験相談・無料体験授業 今すぐお電話ください。